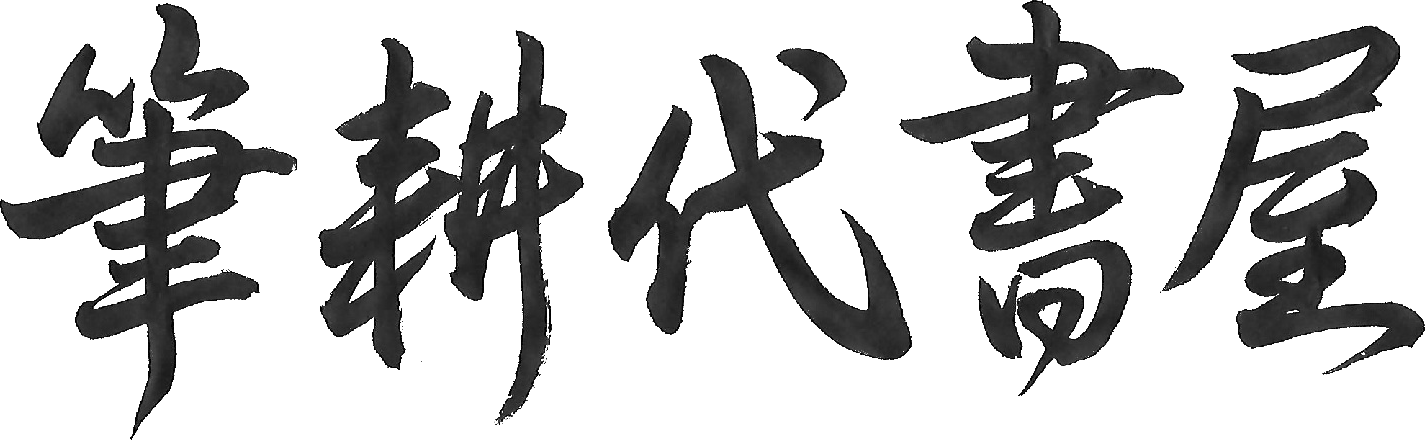過去帳とは
過去帳(かこちょう)は、寺院や家庭で故人の戒名(法名)や命日、俗名、没年齢などを記録する帳面です。主に年忌法要や仏壇での供養の際に使用されます。
宗派や地域によって慣習が異なる場合があるため、菩提寺や地域の慣例に従うことをお勧めします。
■ 基本の記入項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 命日 | 故人が亡くなった日(和暦で記入するのが一般的) |
| 回忌 | 一周忌、三回忌など(不要な場合もある) |
| 戒名/法名 | 僧侶から授かった戒名(浄土真宗では「法名」) |
| 俗名 | 生前の名前(例:山田太郎) |
| 行年 | 享年・満年齢のいずれか。例:「行年 八十六歳」 |
■ 記入例
令和五年 八月十五日
一周忌
釋 清蓮信士
俗名 山田 太郎
行年 八十六歳
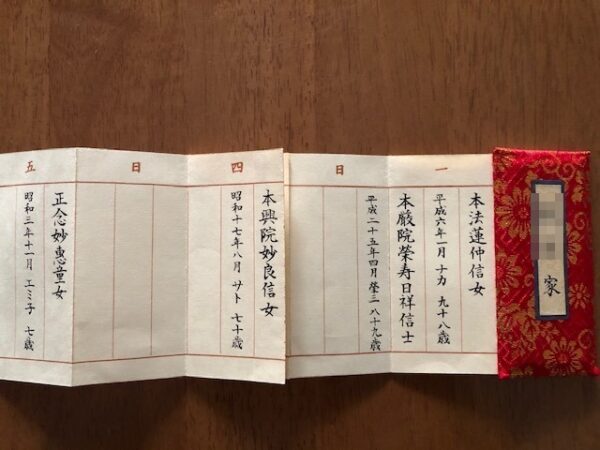
過去帳記入の注意点とポイント
①【命日は和暦で記載する】
-
一般的に西暦より**和暦(令和・平成など)**で記載します。
-
特に寺院や仏事では、年忌法要が和暦で行われるため整合性が取れます。
-
元号が変わると記入が混在しやすいため、「昭和六十三年」「令和五年」など元号+年数を明記しましょう。
②【故人の戒名(法名)は正式に】
-
僧侶から授かった戒名や法名を略さず正式に記載すること。
-
浄土宗などでは「○○院殿○○居士」や「釋○○」など、宗派ごとの書き方に注意。
-
戒名が不明な場合は、空欄にせず「不明」や「戒名未詳」と書いても問題ありません。
③【俗名(生前の名前)も明記】
-
親族間で戒名が分かりにくいことも多いため、俗名も必ず記載します。
-
フルネームで書くのが望ましく、「鈴木 一郎」など姓と名の両方を記載します。
④【行年(享年)は正確に】
-
「行年(ぎょうねん)」とは亡くなった年齢のこと。
-
「享年」は数え年(生まれた時を1歳と数える)
-
「行年」は満年齢(誕生日で加算)で記載されることが多い
-
-
寺院によっては数え年で統一している場合もあるので、事前に確認を。
⑤【記入順序に注意】
-
通常は命日の古い順に記載するのが一般的。
-
家族ごとにまとめる場合や、別冊で系統分けする場合もあり、目的に応じて整理。
-
年忌ごとに参照しやすくするため、インデックスや付箋をつけると便利。
⑥【筆記具は毛筆か筆ペンが基本】
-
過去帳は仏具に近い扱いのため、ボールペンや鉛筆はNGとされます。
-
毛筆が理想ですが、筆ペンでも問題ありません。
-
読みやすく、整った字で書くことが大切です(美しさよりも丁寧さ)。
⑦【記入ミスを防ぐための工夫】
-
書き損じた場合、過去帳は基本的に修正テープや二重線は使わないのが礼儀です。
-
ミスがあると供養の際に混乱を招くため、あらかじめ下書きをするのが安全です。
-
メモ用紙などに書いてから転記すると安心。
-
⑧【宗派ごとの違いに注意】
-
戒名の形式・命日表記・法名の接頭語(例:釋、信女、居士など)などが宗派によって異なります。
-
浄土真宗では「戒名」でなく「法名」と呼び、「釋○○」「○○信士・信女」などの形式。
⑨【保管場所と取り扱い】
-
過去帳は仏壇の中か仏具棚など清浄な場所で保管。
-
日常的に開く場合もありますが、埃や湿気に注意して保護しましょう。
-
年忌や月命日には開いて供養するのが望ましいとされています。
⑩【デジタル記録との併用も可】
-
紙の過去帳と別に、ExcelやWord、クラウドなどに記録することで、家族で情報を共有可能です。
-
ただし、紙の過去帳もきちんと書いておくことで、仏壇での供養の際に意味が増します。
何代にもわたるご先祖様の記録が残る過去帳は、家族にとっての大切な歴史と供養の記録です。正しく、丁寧に記すことで、後の世代への橋渡しにもなります。